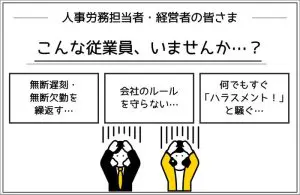【経営幹部向け】事業のありかた
― 事業で何を達成するのか、会社の存在意義―
| 課題 | ・時代の変化に順応できていない ・慣例に従ったまま事業展開しているが先の見通しが立たない ・会社の将来を考える人材がいない ・自社の価値観や存在意義が一部の役員だけのものになっている |
| 到達 | ・価値観・あるべき姿が見つかる ・今後の方向性が共通認識できる ・商品・サービスを通じて何を成し遂げたいのか再認識・共有できる ・自社の存在意義の共有、連携を深める |
| サマリー | ・ワークショップ形式(スライド投影による講義はなし) ・1回2時間×3回開催 ・経営戦略ツールを活用して事業について分析し、討議を実施 |
| 対象者 | ・経営幹部クラス ・経営幹部候補クラス |
| 研修プログラム | 「なぜ、ハラスメントはなくならないのか?」 1.実態に基づき、課題の発見・原因の究明・根本問題の発見 |
【経営幹部向け】ハラスメント研修
― ハラスメントの根本を絶つ、起こらない風土を創る―
| 課題 | ・ハラスメントが発生してしまう根本的な原因から解決したい ・実態に沿ったハラスメント対策を実施できていない |
| 到達 | ・ハラスメント発生の根本的な原因を発見できる ・視座を高くもち、会社・拠点全体の問題は何かを認識できる ・経営幹部・担当者の意識の共有、連携を高め、組織として対策できる |
| サマリー | ・ワークショップ形式(スライド投影による講義はなし) ・1 回2時間 × 3 回 開催 ・会社で発生した実例を通して、コーチング・ファシリテーション形式で 質問と討議を実施 |
| 対象者 | ・経営幹部クラス、 ・各支店のマネジメント・管理職者クラス |
| 研修プログラム | 「なぜ、ハラスメントはなくならないのか?」 1.実態に基づき、課題の発見・原因の究明・根本問題の発見 |
外国人労働者の雇用にあたり、おさえておくべき基礎知識
| 課題 | ・外国人労働者を雇用するには、どのような方法があるのか、基本的事項を知りたい ・外国人労働者を受け入れる際に配慮すべきことは何か |
| 到達 | ・外国人労働者の雇用方法(外国人の就労パターンと在留資格)が把握できる ・外国人労働者採用にあたり、留意するべきことが理解できる ・外国人労働者の労務管理の概観が理解できる |
| サマリー | ・外国人雇用を検討するにあたり、知っておくべき基本的事項について、スライド投影による講義形式 ・外国人労働者にはどのような人がいるのか、就労の種類等、基本的な事項について知識の習得 ・外国人労働者を受け入れる際に留意すべき事項、準備すべき事項についての理解を深める 対面 / オンライン 対応 |
| 対象者 | ・外国人労働者の雇用を検討している会社 ・経営幹部クラス、管理職者クラス |
| 研修プログラム | 外国人労働者を雇用するための、必要な基礎知識を習得する 1.外国人労働者には、どのような人がいるのか ・どのような条件で在留資格が与えられるのか ・「技能実習生」とは何か ・「特定技能」とは何か ・「資格外活動」とは何か 2.外国人労働者の受け入れ ・外国人労働者への配慮 ・外国人労働者を集める媒体 ・採用時に気をつけること ・内定時に気をつけること ・ビザの取得、切替え ・生活基盤を整える ・安心して働く環境づくり |
【管理職者向け】定期面談スキル
― 部下と向き合い行動を引き出す、部下を育てられるスキル―
| 課題 | ・目標・評価面談の基礎知識はあるが、実績が伴わない ・部下の作成した目標設定に、どうフィードバックしたらいいのか悩む ・部下が自身のキャリア像とリンクさせた目標設定をしてくれない |
| 到達 | ・目標管理シートや評価シートの具体的な書き方が指導できる ・部下へ何を期待しているのかが具体的に可視化できる ・伝え方、話の引出し方等、面談のスキルが身につく |
| サマリー | ・スライド投影による講義形式 ・定期面談(目標面談・評価面談)実施にあたり、部下へ目標設定の指導の仕方、設定した目標へのフィードバックの仕方等の、面談スキルの習得 ・対面/ オンライン対応 |
| 対象者 | ・目標や評価を管理する部下を持つ管理職者・リーダークラス |
| 研修プログラム | 部下を育てられる管理職者になるには 1.管理職者の役割は「人を育てる、仕事を育てる」 2.年間の評価サイクルはどのようになっているのか 3.目標管理シートの書き方とは 4.部下への期待の言語化と、部下の行動評価の仕方 5.面談を進めるにあたってのコツ |
【管理職者向け 】 労働法の知識
― 人事労務担当者として、網羅必須な労務知識 ―
「労働法の知識」研修は、毎月2回(1回2時間)を目安に、1年をかけて労働法の基礎と実務について学んでいきます。人事担当者や管理職の方を対象とした、法律の知識に加え実務や事例を交えながら学んでいく研修です。
| 課題 | ・マニュアルや慣例に従った労務管理をしているが、関連する法など、基本的な事柄を改めて学ぶべきだと感じる ・基本的な法律は理解しているつもりだが、自己整理のためにも体系的に労働法と労務管理を把握したい |
| 到達 | ・人事労務管理者として必要な労務知識の棚卸ができる ・人事労務機能と関連する法律を体系的に把握できる ・日々の人事労務管理で判断に迷う事の事例を踏まえた対応法が理解できる |
| サマリー | ・労働法と労務管理について、スライド投影による講義形式 ・全 22 テーマを、 1 回 1 テーマ 2 時間 で開催(推奨開催は 1 ヵ月に2回開催、1年サイクル) ・日々の労務管理で判断に迷う、実例をふまえた質疑応答で、実務に活きる知識を体系的に習得 ・対面 / オンライン 対応 |
| 対象者 | ・人事労務管理を担う管理職者クラス ・人事労務部門の担当者・責任者クラス |
| 研修プログラム | 労働法と労務管理について、全22 テーマを実施 1.雇用契約の原則 2.雇用契約の論点 3.労働法上の雇用契約(有期雇用・無期雇用、委任・請負) 4.雇用契約書と就業規則の機能と仕組 5.採用・異動 配転・出向 6.賃金 7.労働時間・時間外労働 8.変形労働 9.休日と休暇 10.有給休暇 11.休職・復職 12.懲戒・制裁 13.雇用契約の解除 14.労使協定・労働協約 15.団体行動・不当労働行為 16.労働契約法の原則 17.安全配慮義務・健康管理 18.産休・育児休業 19.介護休業 20.高年齢者雇用 21.外国人雇用 22.障碍者雇用 |
【管理職者向け 】 問題社員対応スキル
ハラスメントにならない指導、問題社員対応の正攻法
| 課題 | ・労働トラブルを起こす部下がいる ・問題行動のある部下に指導できない ・ハラスメントが怖くて、問題があっても毅然と対応できない ・ハラスメントとなる言動とならない言動のボーダーラインがわからない |
| 到達 | ・問題行動のある部下について -指導~解雇 or 退職まで流れがわかる -会社として指導できる権利がわかる -面談、指導の経験、スキルが身につく ・ハラスメントと言われない指導法がわかる |
| サマリー | ・スライド投影による講義と、面談・指導のロールプレイ ・雇用契約に基づき、会社に求められる義務と、従業員に求められる権利について理解を深める ・ハラスメントと言われない面談と指導の方法とコツの習得 ・「問題を起こした人」「指導する人」になりきり、労働トラブルを起こした部下との疑似面談の実施 ・言葉の選び方、伝え方、面談・指導の心がまえ等、部下の指導について実務的な知識とスキルの習得 |
| 対象者 | ・部下をもつ管理職者クラス ・労務トラブルに対応する人事労務担当者 |
| 研修プログラム | 指導とハラスメントの違いを理解して、労務トラブル対応力を養成する 1.問題行動のある社員が在籍していると、どのような事態となるのか 労務トラブルは、どのような背景から発生するのか、事例をもって検討する 2.問題行動のある社員の指導のご作法 ・労務管理の原則と、日々の指導~雇用契約終了までの流れ ・ハラスメントと言われない日々の指導方法、言葉の選び方・伝え方 ・労務トラブル面談の特徴をふまえた、面談時に意識するべきことと面談のコツ 3.問題行動のある社員へ指導面談(ロールプレイ) 「問題を起こした人」「指導する人」になりきり、疑似面談を実施 |
⑦新任管理職の労務知識
研修のねらい
「労働法」「労働契約」「就業規程」とは、そもそもどのようなものなのか?職場の中心メンバーが担うべき、現場の労務管理に関する役割とは何か?最近の厚生労働行政の流れはどのようになっているか?を学んでいきます。
⑧新入社員向け労務管理の基礎
研修のねらい
どういった根拠で「働く/働いてもらう」のか?「働く/働いてもらう」にあたって、どんなルール・法律があるのか?ニュースや新聞で話題になっている労働問題とは何か?を学んでいきます。
⑨コミュニケーションスキル
研修のねらい
「聞く」・「見る」・「認める」のコミュニケーションの基本形をみていき、TPOに応じて、コミュニケーションの手段を使い分ける方法を学んでいきます。
⑩労働問題に関する経営判断スキル
研修のねらい
労働トラブルの基本的な知識の習得と、異なる現場で対応に違いが出ないように目線ぞろえを行い、会社としての優先事項と労働トラブルの関係を振り返ります。
⑪問題社員対応スキル
研修のねらい
ロールプレイを取り入れながら問題行動を起こす社員の事例を取り扱い、労基法の基礎を元に、会社としてどう対応すべきかを学んでいきます。
⑫労務トラブルケーススタディー
研修のねらい
様々な労働トラブルケーススタディを扱い、具体的な対応を学んでいきます。
⑬ハラスメント受け流しスキル
研修のねらい
ハラスメントを受ける側としての、社会人としての意識の持ち方や、「単なる文句言いの若手」と誤解されない方法について学んでいきます。若手女性社員対象。